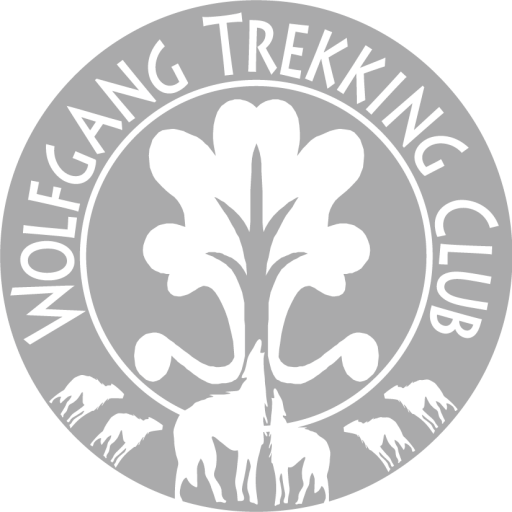そこに山があるから!?
突然、「山に登ろう」なんて思い始めたのは平成一二年頃……登山やるのにはっきりした理由なんてあったらあったである程度病んでいるとは思うし、僕にも理由なんてなかった。まして「そこに山があるから…」とは夢にも思わない。そんな感じであれこれ手を付けるにはこの世界にはアイテムが多すぎてとても時間が足りないだろう。「そこに空があるから……」「そこに海があるから……」「そこにサーキットがあるから……」
考え事の副産物
率直にはただ気が向いたから登ったというだけであり、山頂からの風景などにしても全くどうでもよかった訳ではないが、ほとんどはどうでもよかった。それでは具体的に登山でただ歩く以外に何やっていたのかというとそれは「考え事」であった。だから下山した時にいつも一番疲れているのは「脳ミソ」だったのである。とにかくそのようにして十年位は夢中だったかもしれないが、具体的な考え事がそれほど無尽蔵にあるはずもなくいつしか足も遠のいていった。考え事のネガティブな副産物は孤独感だと気付いて早めに身を引いたというのが正しい。
再燃焼の兆し
そして一度鎮火した情熱が再燃焼するには十分な理由が必要だった。僕はその期間に生涯のパートナーとなる現在の妻と出合う。正確にはずいぶん前に出会っていたのだが、この期間にそれをはっきりとお互いに承認しあったのだ。そしてその妻はアウトドアの活動に対してはかなり強固に無縁の女性で……例えばなだめすかして近場の低山に散歩に連れ出しても、三合目付近で「これを頂上まで登ったとして何になるっていうの?」と言い放ち、そして四合目を最後に下山するという塩梅だった。こちらとしてもそこを押し通すほど山を愛しちゃいない。これほど理屈っぽい僕だが人を説得するという行為に熱意は無く、それは仕事上でも一貫していた。説得されて何かを為した人は、行き詰まった時に多くの場合その責任を他所に転嫁する。付いてくる人は瞬間的についてくるし、また誰一人付いてこない時は、まさに自分自身を冷静に見直した方が良い。とにかくそのような妻を迎えた僕のアウトドア生活は、そうしてある意味一つの結末に向かいかけていた。

邂逅
そんな折我々は後の人生を左右するとは思いもよらず、お気楽にボーダーコリー犬のサニーという新しいメンバーを家族として迎えた。僕としては正直な話それまで犬なんて大の苦手で、詳しく言ってしまうとイヌを飼っている人々がもつ、あの獣との共依存関係に興奮している雰囲気が気持ち悪かった。「まぁ〇〇ちゃんそんなにワンワン吠えちゃって、怖かったでちゅか……」的な。しかしながら妻がかねてからの願いをあきらめずに粘り強く何年もプレゼンし続けた結果の行動ではあったし、僕も最後は腹を括って迎えたのは確かである。
ネットでポチっとやって、千葉から福岡まで航空貨物で飛ばして貰うという、知らない人が聞くと眉をひそめるであろう離れ業で我が家にやってきたサニー。最初の頃の彼は気に入らないものには吼え続け、噛めるものはズタズタになるまで噛み続け、そして何でも無い時は「俺のかあちゃんを出せ!」とばかりに唸り、我々はひと月ばかり途方にくれた。僕の心理状態はもちろん妻には言えなかったが「ほれ、言わんこっちゃねー!どうすんだこれ?」という感じだったがしかし転機は意外と早く二か月後、わりと簡単に訪れた。
運動、規律、愛情
暇つぶし程度に眺めていた動物番組に登場したアメリカのドッグトレーナーのメソッドが気分にしっくりきた事、そして夫婦で近隣の警察犬訓練所にてイヌにではなく我々自身が訓練を受けるというチャンスに恵まれた事、この二点を契機に事態は急に改善していったのである。
学んだ事の主軸は、運動、規律、愛情の三つを正しい順番で過不足なく与える事。またイヌを良い意味で支配する方法論であった。そして僕自身が実践的に理解した内容とは、まず第一に毎日の運動を蔑ろにはしない事。第二に人間社会をまかり通る為に必要な躾は完璧に身に付けさせる事。そして第三に栄養価と健康を最優先に食品を選ぶ事。この3点は人生の後半に差し掛かった我々人間夫婦にとっても幸せに勝ち抜くための必須要素として納得できたのでそれも後押しとなった。だから仔犬のサニーに絶対服従を要求するなど自然な流れだったし、イヌたちをその可愛さのあまり溺愛する気分が全くの”ゼロ”だったところが普通と少し違う自覚はあったけれども、それがイヌにとって不利益だとは全く思わなかった。

芝居じみた登山
件の「1に運動、2に規律、3に愛情」の順番を実践する為には何よりも先ず、絶対服従を要求するのと同時進行でダメ行為を叱るのではなく好ましい行為を褒めるというシーンをふんだんに見つけ出す必要を強く感じた。だが物事を褒めながら絶対服従なんて、そんな芝居じみたシーンが家の中や街中にごろごろ転がっているはずもなく…思いつめた我々はそれならば登山道でもうろついてみようじゃないかという流れで「山」に戻って行ったのである。妻から見ると、一度は自分の哲学に反する行為として登山自体を散々ディスった上で葬ったものの、サニーが自分の故郷として山を歩く様を見て、アウトドアの意味を再発見したように感じたかもしれない。登山と言う行為は、登って下りるまでの行程の中に「生活」の縮刷版が詰まっていた。ある時は平坦な林道をそぞろ歩き、急な崖をよじ登り、そしてパートナーを助け、ある時は足元の不安定なトラバースで他人と道を譲り合い、またあるときは休憩したり食事をしたり……つまりこれらに犬を同行させる事自体「生活」のトレーニングそのものだったのだ。山は考え事をする場所なんかでは無く、まぎれもない生活の場所だった。つまりそういう実践的な意味合いにおいて自分たちが「訪問者」だったと理解して僕は驚き、妻は妻で山を単なる安上がりのアトラクションのように考えていたところへもってきて、僕と同じ事に気付きそして急速に熱中していったのだった。
ヒト族イヌ族
サニーを伴って山を突き進む時、我々は彼らイヌ族が友となる以前の姿に思いを馳せてしまう。獲物を求めて山野を駆け巡り、群れの規律を守りそしてじゃれ合って友情を交換し夜は狭い穴倉で眠る。かたや人の世界に生まれた我々について考えてみると……日々労働し、ルールを守り、隣人を愛し、そして死んでいくという……九割方は同じなのだと理解できてしまうと、サニーに同じ一生を与えられない筈は無いと思えてくる。それを与えきれている限りは、特に「躾」という概念は必要ないことが解ってしまった。こちらのエネルギーが伝わりさえすれば何も問題は起こらないのである。
旅するオオカミの会
最後に、ヒトもイヌも一匹狼というスタイルでは安全も健康もおぼつかなくて必ず家族か仲間を必要とする。そうしたマインドをあえて「ヴルフガング・トレッキング・クラブ」と名付け、自分たち家族の在り方として意識しようというのである。この「旅するオオカミの会」と意味する名が大袈裟かどうかはいつか将来結論に至りましょう、って事で……
城代トシフミ